Kangaroo Point の Cliff-side を歩いている時、家内が私に「ブリスベン川ってどうしていつ来てもこんなに濁っているんだろう?」と言う。
その答えは、遊歩道沿いに点々と置かれているステンレス製のパネルですぐに見つかった。
そこには、こんなことが書かれている。
『……最初にここを訪れた開拓者達は、いつも澄んでいるきれいな川でたくさんの魚やブラック・スワンを見ることができ、岸辺ににはすいれんが咲き大きな木々が聳え立っていた。50年前でさえ、泳げるくらいにきれいで、川沿いには砂浜があった。……今では、開発が進んだために、雨が降るたびに上流の泥や汚染物質が川に流れ込み、ブリスベン川はこんなにも濁ってしまった……。』と。

心臓部をゆったりと流れるブリスベン川はまさにブリスベン市のシンボルであり、上水や工業用水の水源として、City Cat や Cross River Ferry の走る水路として、レクリエーションの場として、そして文化や歴史を語るテーマとして、ブリスベン市民にとってのみならず、そこを訪れる人々にとっても、ブリスベン市と切っても切れない関係にある。
1823年に Oxley がこの川を発見し、2年後現在の North Quay 辺りに植民地の本拠を移して、その後多くの人々がこの地を目指し今日の繁栄を築き上げたのも、この川の魅力に惹かれたからであったし、私達がブリスベンを訪れおこがましくも "Our Fabourite City" とこの街を褒め上げたのも、ブリスベン川の存在が大きな理由の一つになっている。
ブリスベン川は、オーストラリアの南東部に聳える「大分水嶺」 'the Great Dividing Range' の麓に源を発し、Moreton Bay までの約320kmを曲がりくねりながら流れている。

ヨーロッパからの入植者によって発見されるまでは、唯一先住民の一部の部族にしか知られていなかった。その土地と川は彼らの生活を支える源であり、豊富な食糧と共によい漁場を提供していた。
ヨーロッパ人の入植後、川は貿易、輸送、防衛戦略などの上で州都ブリスベンを建設するための重要な役割を果たすようになる。
ダムの建設、砂州の撤去、流域での工業団地や住宅団地の建設などの人間の活動が大きく川を変貌させ、川は次第に茶色く濁っていったのである。
ブリスベン市は、現在のそして将来の人々のために「より健全な水路」 'healthier waterways' を取り戻すべく力を注いでおり、近年ブリスベン川の環境は徐々に改善されつつあるという。
洪水の歴史
このように地域に大きな恩恵を与えてきたブリスベン川だが、それはまた、大きな洪水を繰り返しブリスベン市をはじめその流域の人々を悩まし続けてきた歴史も持っている。
1893年の洪水については「ブリスベンの歴史」の中でも触れたが、最近では1974年1月の洪水が特筆すべきものであろう。
1974年1月26日、ブリスベンは記録的な豪雨に見舞われた。短時間に降った317mmの雨は、排水管を溢れさせそして詰まらせ、いろいろな物を壊し流し去った。停泊中だった大型のオイル・タンカーを含む4隻の船が、コントロールを失ってブリスベン川の下流まで流された。
14000戸を超える住宅が避難を余儀なくされ、その大半は修復不可能なほどの損害を蒙った。空港、鉄道、道路、水路とも使用不能となり、ブリスベンは陸の孤島と化した。泥水と悪臭が消え去るまでに5日間を要したという。
この洪水により、16名の命が失われ、被害総額は3億ドルに達した。
(下の写真は、いずれもクイーンズランド博物館ホームページから)




ブリスベン市は、水害に打ちひしがれた市民を鼓舞し復興への足掛かりを作るため、1982年の Commonwealth Games (過去の大英帝国連邦傘下にあった世界72カ国が参加して4年に1回行なわれる国際スポーツ大会)と1988年の世界万博の2大イベントを成功させ、そして見事に立ち直ったのである。
私達が将来再びブリスベンを訪れる時、ブリスベン川がこれ以上汚れず、少しでもきれいな水が流れていることを期待するものである。
その答えは、遊歩道沿いに点々と置かれているステンレス製のパネルですぐに見つかった。
そこには、こんなことが書かれている。
『……最初にここを訪れた開拓者達は、いつも澄んでいるきれいな川でたくさんの魚やブラック・スワンを見ることができ、岸辺ににはすいれんが咲き大きな木々が聳え立っていた。50年前でさえ、泳げるくらいにきれいで、川沿いには砂浜があった。……今では、開発が進んだために、雨が降るたびに上流の泥や汚染物質が川に流れ込み、ブリスベン川はこんなにも濁ってしまった……。』と。

蛇行する Brisbane River
いつ見ても、こういう風に茶色に濁っている
いつ見ても、こういう風に茶色に濁っている
心臓部をゆったりと流れるブリスベン川はまさにブリスベン市のシンボルであり、上水や工業用水の水源として、City Cat や Cross River Ferry の走る水路として、レクリエーションの場として、そして文化や歴史を語るテーマとして、ブリスベン市民にとってのみならず、そこを訪れる人々にとっても、ブリスベン市と切っても切れない関係にある。
1823年に Oxley がこの川を発見し、2年後現在の North Quay 辺りに植民地の本拠を移して、その後多くの人々がこの地を目指し今日の繁栄を築き上げたのも、この川の魅力に惹かれたからであったし、私達がブリスベンを訪れおこがましくも "Our Fabourite City" とこの街を褒め上げたのも、ブリスベン川の存在が大きな理由の一つになっている。
ブリスベン川は、オーストラリアの南東部に聳える「大分水嶺」 'the Great Dividing Range' の麓に源を発し、Moreton Bay までの約320kmを曲がりくねりながら流れている。

ヨーロッパからの入植者によって発見されるまでは、唯一先住民の一部の部族にしか知られていなかった。その土地と川は彼らの生活を支える源であり、豊富な食糧と共によい漁場を提供していた。
ヨーロッパ人の入植後、川は貿易、輸送、防衛戦略などの上で州都ブリスベンを建設するための重要な役割を果たすようになる。
ダムの建設、砂州の撤去、流域での工業団地や住宅団地の建設などの人間の活動が大きく川を変貌させ、川は次第に茶色く濁っていったのである。
ブリスベン市は、現在のそして将来の人々のために「より健全な水路」 'healthier waterways' を取り戻すべく力を注いでおり、近年ブリスベン川の環境は徐々に改善されつつあるという。
洪水の歴史
このように地域に大きな恩恵を与えてきたブリスベン川だが、それはまた、大きな洪水を繰り返しブリスベン市をはじめその流域の人々を悩まし続けてきた歴史も持っている。
1893年の洪水については「ブリスベンの歴史」の中でも触れたが、最近では1974年1月の洪水が特筆すべきものであろう。
1974年1月26日、ブリスベンは記録的な豪雨に見舞われた。短時間に降った317mmの雨は、排水管を溢れさせそして詰まらせ、いろいろな物を壊し流し去った。停泊中だった大型のオイル・タンカーを含む4隻の船が、コントロールを失ってブリスベン川の下流まで流された。
14000戸を超える住宅が避難を余儀なくされ、その大半は修復不可能なほどの損害を蒙った。空港、鉄道、道路、水路とも使用不能となり、ブリスベンは陸の孤島と化した。泥水と悪臭が消え去るまでに5日間を要したという。
この洪水により、16名の命が失われ、被害総額は3億ドルに達した。
(下の写真は、いずれもクイーンズランド博物館ホームページから)

Edward Street の状況

氾濫したブリスベン川と South Brisbane

Albert Street の状況

Victoria Bridge から South Brisbane 方向を見る
ブリスベン市は、水害に打ちひしがれた市民を鼓舞し復興への足掛かりを作るため、1982年の Commonwealth Games (過去の大英帝国連邦傘下にあった世界72カ国が参加して4年に1回行なわれる国際スポーツ大会)と1988年の世界万博の2大イベントを成功させ、そして見事に立ち直ったのである。
私達が将来再びブリスベンを訪れる時、ブリスベン川がこれ以上汚れず、少しでもきれいな水が流れていることを期待するものである。

 1823年、Mermaid 号で Moreton Bay へ向かったジョン・オクスレー中尉 Lieutenant John Oxley (右図)が Point Skirmish に近づいた時、多くの原住民が興奮して走りよって来るのを見つける。なんと、そのリーダーは白人だった。彼は Thomas Pamphlett、船が難破して7ヶ月間も原住民と一緒に住んでいたのだった。
1823年、Mermaid 号で Moreton Bay へ向かったジョン・オクスレー中尉 Lieutenant John Oxley (右図)が Point Skirmish に近づいた時、多くの原住民が興奮して走りよって来るのを見つける。なんと、そのリーダーは白人だった。彼は Thomas Pamphlett、船が難破して7ヶ月間も原住民と一緒に住んでいたのだった。








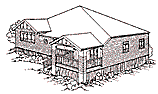








 そんな会話の途中で耳にしたいくつかの Aussie Slang の中で、何となく「かわいいな!」と思ったのが、名詞の語尾に "ie" を付けて一種の親しみを込めて表現する習慣だった。
そんな会話の途中で耳にしたいくつかの Aussie Slang の中で、何となく「かわいいな!」と思ったのが、名詞の語尾に "ie" を付けて一種の親しみを込めて表現する習慣だった。




